
アルマジロトカゲとデプレッサイワトカゲの2025年-2026年のクーリングの計画と途中経過をまとめました。
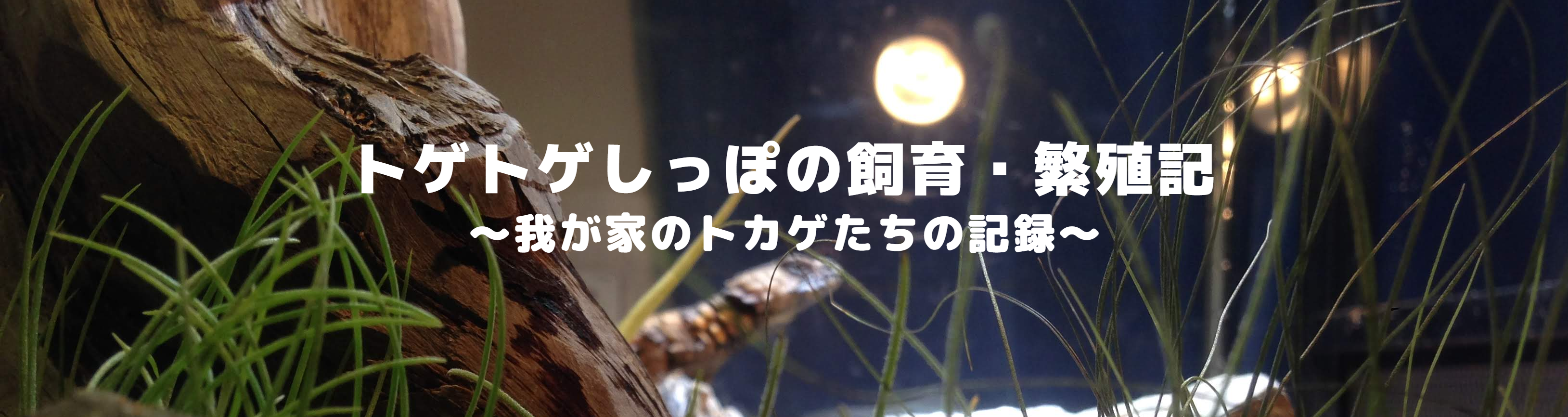

アルマジロトカゲとデプレッサイワトカゲの2025年-2026年のクーリングの計画と途中経過をまとめました。

アルマジロトカゲのクーリング明けから出産までの記録です。 2024年にうまく行かなかったことを踏まえて、2025年は無事に繁殖させることができ、安堵しました。

デプレッサイワトカゲの2025年出産までの記録をまとめました。 1匹ずつではありますが、2024年から連続の繁殖成功となり、先代デプレッサに顔向けできる成果になったと思います。

アルマジロトカゲとデプレッサイワトカゲに関するベビーの成長速度についてまとめました。 ベビーで購入した際にどの程度の速さで大きくなっていくかの参考になれば幸いです。